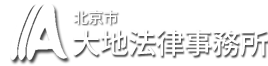жЦ∞жФњз≠ЦпЉЪжЃЛж•≠жЩВйЦУеИґйЩРеИґеЇ¶гБ®дЉБж•≠гБЃеЃЯеЛЩеѓЊењЬ
ињСй†ГгАБDJIгАБMideaгАБгГПгВ§гВҐгГЉгГЂгБ™гБ©гБЃе§ІжЙЛдЉБж•≠гБМгАМз§ЊеУ°гВТеЉЈеИґзЪДгБЂеЃЪжЩВйААз§ЊгБХгБЫгАБйБОеЇ¶гБ™жЃЛж•≠гВТгБХгБЫгБ™гБДгАНгБ®гБДгБЖеПЦгВКзµДгБњгВТеІЛгВБгБЯгБУгБ®гБМи©±й°МгБ®гБ™гВКгАБе§ІгБНгБ™ж≥®зЫЃгВТйЫЖгВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБ3жЬИ16жЧ•гБЂдЄ≠еЫљдЄ≠е§ЃеЉБеЕђеЇБгБ®еЫљеЛЩйЩҐеЉБеЕђеЇБгБМзЩЇи°®гБЧгБЯгАОжґИи≤їжМѓиИИзЙєеИ•и°МеЛХи®ИзФїгАПпЉИдї•дЄЛгАМи°МеЛХи®ИзФїгАНгБ®гБДгБЖгАВпЉЙгБІгВВгАБгАМеКіеГНиАЕгБЃдЉСжБѓгГїдЉСжЪЗгБЃж®©еИ©гВТж≥ХзЪДгБЂдњЭйЪЬгБЧгАБйБХж≥ХгБЂеКіеГНжЩВйЦУгВТеїґйХЈгБЧгБ¶гБѓгБ™гВЙгБ™гБДгАНгБ™гБ©гБЃи¶Бж±ВгБМжШОи®ШгБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВжЬђз®њгБІгБѓгАБгБУгВМгВЙгБЃдЉБж•≠гБЂгВИгВЛгАМжЃЛж•≠жЩВйЦУеИґйЩРгАНгБЃиГМжЩѓгБ®и°МеЛХи®ИзФїгБЃжДПеЫ≥гБЂгБ§гБДгБ¶з∞°жљФгБЂиІ£и™ђгБДгБЯгБЧгБЊгБЩгАВ
1. гАМжЃЛж•≠жЩВйЦУеИґйЩРгГїйБОеЇ¶гБ™жЃЛж•≠з¶Бж≠ҐгАНеИґеЇ¶гБЃиГМжЩѓ
пЉИ1пЉЙеЊУж•≠еУ°гБЃеКіеГНж®©зЫКдњЭи≠ЈгБЂйЦҐгБЩгВЛж≥Хдї§й†ЖеЃИи¶БиЂЛ
ињСеєігАБдЄАйГ®гБЃдЉБж•≠гБІгБѓйБХж≥ХгБ™еКіеГНжЩВйЦУгБЃеїґйХЈгВДгАБи¶ЛгБИгБ™гБД嚥гБІгБЃжЃЛж•≠пЉИгВµгГЉгГУгВєжЃЛж•≠пЉЙгБМи°МгВПгВМгАБйБОеКігБЂгВИгВЛз™БзДґж≠їгВДгБЖгБ§зЧЕгБ™гБ©гБЃеХПй°МгБМзЩЇзФЯгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВзПЊи°МгБЃеКіеГНж≥ХгБІгБѓгАБеКіеГНиАЕгБЃеКіеГНжЩВйЦУгВДдЉСжБѓгГїдЉСжЪЗгБЃж®©еИ©гВТи¶ПеЃЪгБЧгАБдЉБж•≠гБМжБ£жДПзЪДгБЂйБОеЇ¶гБ™жЃЛж•≠гВТеЉЈгБДгВЛгБУгБ®гВТз¶Бж≠ҐгБЧгБ¶гБКгВКгАБеКіеГНиАЕгБЃйБ©ж≠£гБ™жЃЛж•≠жЩВйЦУгВТдњЭи®ЉгБЩгВЛгБУгБ®гБІгАБеКіеГНиАЕгБЃеБ•еЇЈгВТдњЭи≠ЈгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБХгВЙгБЂгАБEUгБМ2024еєіжЬЂгБЂжО°жКЮгБЧгБЯгАМеЉЈеИґеКіеГНз¶Бж≠Ґж≥Хж°ИгАНгБѓгАБEUеРСгБСгБЃиЉЄеЗЇдЉБж•≠гБЂгВВељ±йЯњгВТеПКгБЉгБЧгБЊгБЧгБЯгБМгАБгБУгБЃгАМжЃЛж•≠жЩВйЦУеИґйЩРгАНгБЂйЦҐгБЩгВЛжЦ∞жФњз≠ЦгБѓгАБзПЊеЬ∞дЉБж•≠гБЃеКіеГНеЯЇжЇЦгБМеЫљйЪЫеЯЇжЇЦгБЂгБ™гВЛгБУгБ®гВТеК†йАЯгБХгБЫгАБзЂґдЇЙеКЫгБЃеРСдЄКгБЂзєЛгБМгВЛгВВгБЃгБ®иАГгБИгВЙгВМгБЊгБЩгАВ
пЉИ2пЉЙжґИи≤їйЬАи¶БгБЃдњГйА≤
зПЊеЬ®гБЃзµМжЄИзКґж≥БгБІгБѓжґИи≤їгБЃдЉЄгБ≥гБМйИНеМЦгБЧгБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБеКіеГНиАЕгБЃжЃЛж•≠жЩВйЦУгВТжЄЫгВЙгБЩгБУгБ®гБІиЗ™зФ±жЩВйЦУгБМеҐЧгБИгАБгГЧгГ©гВ§гГЩгГЉгГИгБЃеЕЕеЃЯгВДдљЩжЪЗжґИи≤їгБЃжіїжАІеМЦгБМжЬЯеЊЕгБХгВМгБЊгБЩгАВгБУгВМгБЂгВИгВКгАБй£≤й£ЯгАБи¶≥еЕЙгАБжЦЗеМЦгАБгВ®гГ≥гВњгГЉгГЖгВ§гГ≥гГ°гГ≥гГИгБ™гБ©гБЃж•≠зХМгБМжИРйХЈгБЩгВЛеПѓиГљжАІгБМи¶ЛиЊЉгБЊгВМгБЊгБЩгАВ
пЉИ3пЉЙеЊУж•≠еУ°гБЃењГиЇЂгБЃеБ•еЇЈзґ≠жМБ
йБОеЇ¶гБ™жЃЛж•≠гВТжКСеИґгБЩгВЛгБУгБ®гБІеЊУж•≠еУ°гБЃдЉСжБѓж®©гБМ祯дњЭгБХгВМгАБиЇЂдљУзЪДгГїз≤Њз•ЮзЪДгБ™еБ•еЇЈгБМзґ≠жМБгБХгВМгБЊгБЩгАВгБУгВМгБѓгАБ3жЬИ9жЧ•гБЂйЦЛгБЛгВМгБЯзђђ14еЫЮеЕ®еЫљдЇЇж∞Сдї£и°®е§ІдЉЪзђђ3еЫЮдЉЪи≠∞гБІеЫљеЃґи°ЫзФЯеБ•еЇЈеІФеУ°дЉЪгБМжПРж°ИгБЧгБЯгАМдљУйЗНзЃ°зРЖеєігАН3гВЂеєіи®ИзФїгБЂгВВеѓЊењЬгБЩгВЛеЛХгБНгБІгБЩгАВ
пЉИ4пЉЙйЫЗзФ®гБЃеЭЗи°°дњГйА≤
жЃЛж•≠гВТеЉЈеИґгБЧгБ™гБДгБУгБ®гБІдЉБж•≠гБѓеКіеГНеКЫгВТгГРгГ©гГ≥гВєгВИгБПйЕНеИЖгБЩгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гВКгАБзЯ≠жЬЯзЪДгБЂгБѓеРМжІШгБЃж•≠еЛЩгБЂгВВеКіеГНеКЫгБЃеҐЧеК†гБМењЕи¶БгБ®гБ™гВЛгБЯгВБгАБз§ЊдЉЪеЕ®дљУгБЃйЫЗзФ®ж©ЯдЉЪгБМеҐЧеК†гБЧгАБйЫЗзФ®гБЃеЭЗи°°гБМдњГйА≤гБХгВМгВЛгБУгБ®гБМжЬЯеЊЕгБХгВМгБЊгБЩгАВ
2. зПЊеЬ∞гБЃжЧ•з≥їдЉБж•≠гБМж§Ьи®ОгБЩгБєгБНгГЭгВ§гГ≥гГИ
пЉИ1пЉЙж≥Хдї§й†ЖеЃИгБЃеЊєеЇХгБ®йБ©еИЗгБ™еѓЊењЬ
гБУгБЃгАМи°МеЛХи®ИзФїгАНгБЃжЦљи°МеЊМгАБеРДеЬ∞гБЃеКіеГНи°МжФњзЫ£зЭ£зЃ°зРЖйГ®йЦАгБМжЬЙ絶дЉСжЪЗгВДжЃЛж•≠жЩВйЦУгБЃжМѓжЫњгАБжЃЛж•≠дї£гБЃжФѓжЙХгБДгБ™гБ©гБЃйБµеЃИгБЂгБ§гБДгБ¶гБЃзЫ£зЭ£зЃ°зРЖгВТеЉЈеМЦгБЩгВЛеПѓиГљжАІйЂШгБДгБ®жАЭгВПгВМгБЊгБЩгАВ
еРДжЧ•з≥їдЉБж•≠гБѓгАБйБХж≥ХгБ™жЃЛж•≠жЩВйЦУгБЃеїґйХЈгБЂгВИгВЛж≥ХзЪДгГ™гВєгВѓгВТеЫЮйБњгБЩгВЛгБЯгВБгАБзПЊеЬ∞еЉБи≠Је£ЂгБЃгВµгГЭгГЉгГИгВТеПЧгБСгБ§гБ§гАБиЗ™з§ЊгБЃдЇЛж•≠гБЃзЙєжАІгБЂењЬгБШгБ¶йЫЗзФ®жЦєйЗЭгВТи¶ЛзЫігБЩењЕи¶БгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБгГ°гГЉгГЂгВДйЫїи©±гБІгБЃж•≠еЛЩжМЗз§ЇгБЂгВИгВЛе∞±ж•≠жЩВйЦУе§ЦгБЃгАМи¶ЛгБИгБ™гБДжЃЛж•≠пЉИгВµгГЉгГУгВєжЃЛж•≠пЉЙгАН гБЂгВВж≥®жДПгБМењЕи¶БгБІгБЩгАВ
гБ™гБКгАБгБУгБЃжЦ∞жФњз≠ЦгБѓжЃЛж•≠гВТеЃМеЕ®гБЂз¶Бж≠ҐгБЩгВЛгВВгБЃгБІгБѓгБ™гБПгАБзФЯзФ£зПЊе†ігБІгБЃзЈКжА•еѓЊењЬгВДгБЭгБЃдїЦж•≠еЛЩгБЂгБКгБДгБ¶ењЕи¶БгБ™е†іеРИгБЂгБѓгАБж≥ХеЊЛгБЃзѓДеЫ≤еЖЕпЉИдЊЛгБИгБ∞еє≥жЧ•гБѓ1жЧ•3жЩВйЦУдї•еЖЕгАБжЬИйЦУ36жЩВйЦУдї•еЖЕгБ™гБ©пЉЙгБІжЃЛж•≠гВТжМЗз§ЇгБЩгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩ
пЉИ2пЉЙ絶дЄОеИґеЇ¶гБ™гБ©гБЃеЖНжІЛзѓЙ
дЄАйГ®гБЃи£љйА†ж•≠гБІгБѓгАБжЃЛж•≠дї£гБМи≥ГйЗСгБЃдЄАеЃЪеЙ≤еРИгВТеН†гВБгВЛгВ±гГЉгВєгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВжЃЛж•≠еЙКжЄЫгБЂгВИгВК絶дЄОгБМе§ІеєЕгБЂжЄЫе∞СгБЩгВЛгБ®гАБеЊУж•≠еУ°гБМгБЭгВМгВТзРЖзФ±гБЂз§ЊдЉЪдњЭйЩЇгВДдљПеЃЕз©НзЂЛйЗСгАБжЃЛж•≠дї£гАБзТ∞еҐГеХПй°МгБ™гБ©гБЃзЃ°зРЖгВДеКіеЛЩгБЃеХПй°МгБЂгБ§гБДгБ¶гАБдЉБж•≠гБЂеѓЊгБЧиЛ¶жГЕзФ≥зЂЛгБ¶гВДеСКзЩЇгАБдї≤и£БзФ≥зЂЛгБ¶гВТгБЩгВЛеПѓиГљжАІгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгБЭгБЃгБЯгВБгАБжЧ•з≥їдЉБж•≠гБѓењЕи¶БгБЂењЬгБШгБ¶зПЊеЬ∞еЉБи≠Је£ЂгБ®гБ®гВВгБЂдЇЇдЇЛи©ХдЊ°еИґеЇ¶гВДзЫ£зЭ£зЃ°зРЖеИґеЇ¶гВТи¶ЛзЫігБЧгАБ絶дЄОдљУз≥їгВТеЖНжІЛзѓЙгБЩгВЛгБ™гБ©гБЧгБ¶еЊУж•≠еУ°гБЃдЄНжЇАгВТиІ£жґИгБЧгАБгГ™гВєгВѓгВТиїљжЄЫгБЩгВЛжЦєж≥ХгВТж§Ьи®ОгБЩгВЛгБУгБ®гВВењЕи¶БгБІгБЩгАВ
絶дЄОдљУз≥їгБ™гБ©гБЃжІЛзѓЙгБѓгАБеНШзіФгБ™еЊУж•≠еУ°зЃ°зРЖгБЃеХПй°МгБІгБѓгБ™гБПгАБеРДеЬ∞жЦєгБІжЦљи°МгБХгВМгБ¶гБДгВЛ絶дЄОгБЂйЦҐгБЩгВЛж≥Хдї§гВДеЃЯеЛЩдЄКгБЃж≥ХеЯЈи°МжФњз≠ЦгБЂгВВйЦҐйА£гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЭгБЃгБЯгВБгАБж≥Хдї§йБХеПНгБМгБВгБ£гБЯе†іеРИгБѓеЊУж•≠еУ°гБ®гБЃгГИгГ©гГЦгГЂгБЂзЩЇе±ХгБЧгВДгБЩгБПгАБдЉБж•≠гБЂгБ®гБ£гБ¶гБѓеКіеЛЩдЄКгБЃжљЬеЬ®зЪДгГ™гВєгВѓгБ®гБ™гВЛгБУгБ®гБЂж≥®жДПгБМењЕи¶БгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
пЉИ3пЉЙеЊУж•≠еУ°гБЃењГиЇЂгБЃеБ•еЇЈгВТйЗНи¶ЦгБЧгАБдЉБж•≠жЦЗеМЦгВТеЖНжІЛзѓЙгБЩгВЛ
гАМ00еЊМгАНпЉИ2000еєідї•йЩНзФЯгБЊгВМпЉЙгБ™гБ©гБЃиЛ•еєіеКіеГНиАЕгБѓгГѓгГЉгВѓгГ©гВ§гГХгГРгГ©гГ≥гВєгВТйЗНи¶ЦгБЩгВЛеВЊеРСгБМгБВгВЛгБЯгВБгАБеЊУжЭ•гБЃгАМжЃЛж•≠жЦЗеМЦгАНгБМжЃЛгВЛдЉБж•≠гБѓдЇЇжЭРгБЃзҐЇдњЭгВДеЃЪзЭАгБМйЫ£гБЧгБПгБ™гВЛеПѓиГљжАІгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВдїКеЊМгАБеБ•еЕ®гБ™дЉБж•≠жЦЗеМЦпЉИйА±дЉС2жЧ•еИґгВДгГХгГђгГГгВѓгВєгВњгВ§гГ†еИґеЇ¶гБ™гБ©пЉЙгБѓдЉБж•≠гБЃзЂґдЇЙеКЫгБЃдЄАгБ§гБ®гБ™гВЛгБУгБ®гВВиАГгБИгВЙгВМгАБгБУгВМгБѓеЊУж•≠еУ°гБЃеЄ∞е±ЮжДПи≠ШгВТйЂШгВБгВЛгБУгБ®гБЂгВВгБ§гБ™гБМгВКгБЊгБЩгАВгБЭгБЃгБЯгВБгАБдЉБж•≠гБЂгБѓгГ°гГ≥гВњгГЂгГШгГЂгВєгВЂгВ¶гГ≥гВїгГ™гГ≥гВ∞гВДз§ЊеЖЕгВ§гГЩгГ≥гГИгАБдЉСжЪЗеПЦеЊЧгБЃе•®еК±гБ™гБ©гВТйАЪгБШгБ¶дЉБж•≠жЦЗеМЦгВТеЖНжІЛзѓЙгБЧгАБдЇЇжЭРгВТзН≤еЊЧгГїеЃЪзЭАгБХгБЫгВЛгБУгБ®гБМж±ВгВБгВЙгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
пЉИ4пЉЙжЯФиїЯгБ™еИЖжХ£дЉСжЪЗгБ™гБ©гБЃеИґеЇ¶гБЃе∞ОеЕ•
з§ЊеУ°гБМдЄАжЦЙгБЂдЉСжЪЗгВТеПЦеЊЧгБЩгВЛгБУгБ®гБЂгВИгВЛж•≠еЛЩгБЄгБЃељ±йЯњгВТйБњгБСгВЛгБЯгВБгАБдЉБж•≠гБѓиЗ™з§ЊгБЃзКґж≥БгБЂењЬгБШгБ¶еєіжђ°жЬЙ絶дЉСжЪЗгБ®дЄЙйА£дЉСгВТзµДгБњеРИгВПгБЫгБЯгАМеИЖжХ£дЉСжЪЗгАНгБЃе∞ОеЕ•гВТж§Ьи®ОгБЧгБ¶гВВжІЛгБДгБЊгБЫгВУгАВдљЖгБЧгАБеКіеГНдЇЙи≠∞гБЃзЩЇзФЯгВТеЫЮйБњгБЊгБЯгБѓиїљжЄЫгБЩгВЛгБЯгВБгБЂгБѓгАБдЉБж•≠гБѓгАМеИЖжХ£дЉСжЪЗгАНгБЂгБ§гБДгБ¶ж≥ХгБЃеЃЪгВБгВЛж∞СдЄїзЪДжЙЛзґЪгБНгВТзµМгБ¶и¶ПеЃЪгВТз≠ЦеЃЪгБЧгАБеЊУж•≠еУ°гБЄгБЃжЫЄйЭҐгБЂгВИгВЛеРМжДПгВТеЊЧгВЛгБУгБ®гБМењЕи¶БгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
пЉИ5пЉЙAIгВДиЗ™еЛХеМЦгГДгГЉгГЂгАБжЦ∞жКАи°УгБЃжіїзФ®гБЂгВИгВЛеКєзОЗеРСдЄК
2025еєігБЃжФњеЇЬжіїеЛХ冱еСКгБІгБѓгАБгАМдЄНи¶БгБ™йБОеЇ¶гБЃзЂґдЇЙгАНгВТжШѓж≠£гБЧгАБдЉБж•≠гБЃзЂґдЇЙиїЄгВТгАМжЩВйЦУгАНгБЛгВЙгАМеКєзОЗгАНгБЂиїҐжПЫгБЩгВЛгБУгБ®гБМжПРи®АгБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВдїКеЊМгАБеНШзіФгБ™еКіеГНжЩВйЦУгБЃеїґйХЈгБ™гБ©гБЂгВИгВЛдЊ°ж†ЉеД™дљНжАІгБѓдљОдЄЛгБЩгВЛгБ®иАГгБИгВЙгВМгБЊгБЩгАВдЉБж•≠гБѓеКєзОЗгБЃеРСдЄКгБ®ж•≠еЛЩйБВи°МгБЃгГРгГ©гГ≥гВєгВТ殰糥гБЩгВЛењЕи¶БгБМгБВгВКгАБAIгГДгГЉгГЂгВДгВєгГЮгГЉгГИж©ЯеЩ®гАБж•≠еЛЩиЗ™еЛХеМЦжКАи°УгБЃе∞ОеЕ•гБЂгВИгВКгАБдЉБж•≠зЃ°зРЖгВДзФЯзФ£гГҐгГЗгГЂгВТи¶ЛзЫігБЧгАБж•≠еЛЩгГХгГ≠гГЉгВТеКєзОЗеМЦгБЩгВЛгБ™гБ©гБЧгБ¶гАБеКіеГНиАЕгБЃж•≠еЛЩеКєзОЗгВТеРСдЄКгБХгБЫгАБдЉБж•≠и£љеУБгБЃзЂґдЇЙеКЫгВТйЂШгВБгВЛгБУгБ®гБМдЄНеПѓжђ†гБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
дљЬжИРжЧ•пЉЪ2025еєі03жЬИ18жЧ•