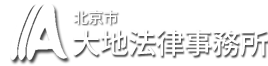йҖҹе ұпјҡж°‘й–“зөҢжёҲдҝғйҖІжі•иҚүжЎҲгҒ®дәҢж¬ЎеҜ©иӯ°зЁҝгҒҢеҜ©иӯ°е…ҘгӮҠ
2025е№ҙ2жңҲ24ж—ҘгҖҒ第14жңҹе…ЁеӣҪдәәж°‘д»ЈиЎЁеӨ§дјҡеёёеӢҷ委員дјҡ第14еӣһдјҡиӯ°гҒҢеҢ—дә¬гҒ§й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҖҒж°‘й–“зөҢжёҲдҝғйҖІжі•иҚүжЎҲгҒ®дәҢж¬ЎеҜ©иӯ°зЁҝпјҲд»ҘдёӢгҖҢдәҢж¬ЎеҜ©иӯ°зЁҝгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮпјүгҒҢеҜ©иӯ°дәӢй …гҒЁгҒ—гҒҰжҸҗеҮәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҪ“и©ІдәҢж¬ЎеҜ©иӯ°зЁҝгҒҜдёҖж¬ЎеҜ©иӯ°зЁҝгӮ’гғҷгғјгӮ№гҒ«дёҖйғЁгҒ®еҶ…е®№гҒ«иӘҝж•ҙгӮ’еҠ гҒҲгҖҒеӣҪ家гҒ®з«Ӣжі•йқўгҒӢгӮүж°‘й–“зөҢжёҲгҒҠгӮҲгҒігғ“гӮёгғҚгӮ№з’°еўғгҒ®жі•жІ»йқўгҒ®дҝқйҡңгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒж°‘й–“дјҒжҘӯгҒ®зҷәеұ•гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰеӨ§гҒ„гҒ«гғЎгғӘгғғгғҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ“гҒ§д»ҠеӣһгҒҜгҖҒдәҢж¬ЎеҜ©иӯ°зЁҝгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжіЁзӣ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰз°ЎжҪ”гҒ«зҙ№д»ӢгҒ„гҒҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
1.дјҒжҘӯгҒ«й–ўгӮҸгӮӢиЎҢзӮәгҒёгҒ®гҖҢдёҚйҒЎеҸҠгҒ®еҺҹеүҮгҖҚгӮ’йҒ©з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гҒ“гҒ®гҖҢдёҚйҒЎеҸҠгҒ®еҺҹеүҮгҖҚжқЎй …гҒ®зӣ®зҡ„гҒҜгҖҒдё»гҒ«дјҒжҘӯзөҢе–¶гҒ®иҰӢйҖҡгҒ—гӮ’дҝқйҡңгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠдјҒжҘӯгҒ®йҒҺеҺ»гҒ®иЎҢзӮәгӮ’ж–°гҒҹгҒӘиҰҸе®ҡгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиҝҪеҸҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒжі•еҫӢиҰҸе®ҡгӮ„ж”ҝзӯ–гҒ®еӨүеҢ–гҒҢдјҒжҘӯгҒ®йҒҺеҺ»гҒ®иЎҢзӮәгӮ’гҖҢи’ёгҒ—иҝ”гҒҷгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгғӘгӮ№гӮҜгӮ’и»ҪжёӣгҒҫгҒҹгҒҜеӣһйҒҝгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒ2025е№ҙгҒ«зҷәеҠ№гҒ•гӮҢгҒҹжі•еҫӢгӮ’2024е№ҙгҒ«дјҒжҘӯгҒҢиЎҢгҒЈгҒҹеҗҲжі•зҡ„гҒӘзөҢе–¶иЎҢзӮәгҒ®еҮҰзҪ°гҒ«йҒ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжі•и§ЈйҮҲгҒ®иӘҝж•ҙгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҒҺеҺ»гҒ®еҗҲжі•зҡ„гҒӘиЎҢзӮәгҒҢгҖҒзӘҒ然йқһеҗҲжі•гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгӮ„жҮёеҝөгӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
дјҒжҘӯгҒ®жіЁж„ҸзӮ№пјҡ
пјҲ1пјүгҒ“гҒ®гҖҢдёҚйҒЎеҸҠгҒ®еҺҹеүҮгҖҚжқЎй …гҒ®йҒ©з”ЁзҜ„еӣІгҒҜгҖҒиЈҒеҲӨгӮ„жӨңеҜҹж©ҹж§ӢгҒҢиЎҢгҒҶжҚңжҹ»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе…·дҪ“зҡ„гҒӘйҒ©з”Ёжі•еҫӢгҒ®и§ЈйҮҲпјҲеҸёжі•и§ЈйҮҲгӮ„дәӢжЎҲгӮ¬гӮӨгғүгғ©гӮӨгғіпјүгҒ®гҒҝгҒ«йҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжі•еҫӢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҜйҒ©з”ЁзҜ„еӣІгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢдёҚжӯЈз«¶дәүгҖҚгҒ®жҰӮеҝөгҒҢж–°гҒҹгҒ«иӘҝж•ҙгҒ•гӮҢгҒҹе ҙеҗҲгҖҒдјҒжҘӯгҒҢиӘҝж•ҙеүҚгҒ«иЎҢгҒЈгҒҹиЎҢзӮәгҒҢгҖҢдёҚеҪ“иЎҢзӮәгҖҚгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиӘҝж•ҙеүҚгҒ®еҹәжә–гӮ’йҒ©з”ЁгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
пјҲ2пјүж–°гҒҹгҒӘи§ЈйҮҲгҒҢдјҒжҘӯгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰжңүеҲ©гҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲпјҲзҪ°йҮ‘еүІеҗҲгҒ®еј•гҒҚдёӢгҒ’гҒӘгҒ©пјүгҖҒдјҒжҘӯгҒҜйҒҺеҺ»гҒ®зҙӣдәүеҮҰзҗҶгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж–°гҒҹгҒӘи§ЈйҮҲгҒ®йҒ©з”ЁгӮ’дё»ејөгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжҗҚеӨұгӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
2.жҒЈж„Ҹзҡ„гҒӘиІ»з”ЁеҫҙеҸҺгӮ„зҪ°йҮ‘гҒ®иҰҸеҲ¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
дәҢж¬ЎеҜ©иӯ°зЁҝгҒ§гҒҜгҖҒгҒ„гҒӢгҒӘгӮӢзө„з№”гӮ„еӣЈдҪ“гӮӮж°‘й–“зөҢжёҲзө„з№”гҒ«еҜҫгҒ—йҒ•жі•гҒӘиІ»з”ЁеҫҙеҸҺгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒҡгҖҒгҒҫгҒҹжі•еҫӢгӮ„жі•иҰҸгҒ®ж №жӢ гҒҢгҒӘгҒ„зҪ°йҮ‘гӮ’科гҒ—гҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢжҸҗиө·гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒжі•еҹ·иЎҢе®ҳгҒҢгҖҢиЎӣз”ҹеҹәжә–гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒ“гҒЁгӮ’зҗҶз”ұгҒ«дјҒжҘӯгҒ«10дёҮе…ғгҒ®зҪ°йҮ‘гӮ’科гҒҷе ҙеҗҲгҖҒй–ўйҖЈжі•иҰҸгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзҪ°йҮ‘гҒ®жңҖй«ҳйЎҚеҹәжә–гҒҜ5дёҮе…ғгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜйҒ•жі•гҒӘзҪ°йҮ‘гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒдјҒжҘӯгҒ«гҖҢгӮ№гғқгғігӮөгғјж–ҷгӮ„еҜ„д»ҳйҮ‘гҖҚгҒӘгҒ©гҒ®жҸҗдҫӣгӮ’иҰҒжұӮгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒж°‘й–“зөҢжёҲзө„з№”гҒ«иІЎзү©гӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеӣҪ家гҒҢз«Ӣжі•еҪўејҸгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж”ҝеәңеҸҠгҒігҒқгҒ®д»–зө„з№”гҒ®иЎҢж”ҝиЎҢзӮәгӮ’иҰҸеҲ¶гҒ—гҖҒе…¬жЁ©еҠӣгҒ«гӮҲгӮӢж°‘е–¶дјҒжҘӯгҒ®з”ҹз”ЈгӮ„зөҢе–¶гҒёгҒ®еӨ–зҡ„е№ІжёүгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢйҷҗгӮҠжёӣе°‘гҒ—гҖҒж”ҝеәңгҒ«гӮҲгӮӢгӮҖгӮ„гҒҝгҒӘиІ»з”ЁеҫҙеҸҺгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гӮ’жҠ‘еҲ¶гҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮеҗҢжҷӮгҒ«дјҒжҘӯгҒҜж”ҝеәңгҒ«еҜҫгҒ—й–ўйҖЈгӮөгғјгғ“гӮ№дәӢй …гҒЁгҒқгҒ®иІ»з”Ёеҹәжә–гҒ®е…¬й–ӢгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғ“гӮёгғҚгӮ№з’°еўғгӮ’йҖҸжҳҺеҢ–гҒ—гҖҒиЈҸеҸ–еј•гҒ®зҷәз”ҹгӮ’еӣһйҒҝгҖҒгҒҫгҒҹжёӣе°‘гҒ•гҒӣгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е…Ҳж—Ҙе®ҹж–ҪгҒ•гӮҢгҒҹж°‘й–“дјҒжҘӯеә§и«ҮдјҡгҒ§гӮӮгҖҒиҝ‘гҒ„е°ҶжқҘгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдәәе·ҘзҹҘиғҪгӮ„ж–°гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҖҒй«ҳе“ҒиіӘиЈҪйҖ жҘӯеҸҠгҒіж–°иіӘз”ҹз”ЈеҠӣгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№жҘӯгҒӘгҒ©гҒ®еҲҶйҮҺгҒ®зҷәеұ•еӮҫеҗ‘гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮд»ҠеҫҢгҖҒгҖҺж°‘й–“зөҢжёҲдҝғйҖІжі•гҖҸгҒ®е…¬еёғгҒЁж–ҪиЎҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж°‘й–“дјҒжҘӯгҒҜеёӮе ҙ競дәүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮҲгӮҠеӨҡгҒҸгҒ®жі•жІ»йқўгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдҝқйҡңгӮ’еҫ—гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒдјҒжҘӯгҒҢйҒ•жі•иЎҢзӮәгғӘгӮ№гӮҜгӮ’и»ҪжёӣгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒдјҒжҘӯеҒҙгҒ«гӮӮгӮҲгӮҠдёҖеұӨгҒ®жі•д»ӨйҒөе®ҲгӮ„гӮігғігғ—гғ©гӮӨгӮўгғігӮ№зөҢе–¶гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
дҪңжҲҗж—Ҙпјҡ2025е№ҙ02жңҲ26ж—Ҙ