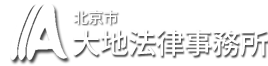中国の婚姻・家庭財産分割ルールの変更点 -NEW-
2025年1月15日、最高人民法院は『「中華人民共和国民法典」婚姻家庭編の適用に関する最高人民法院による解釈(二)』(以下『解釈二』という。)を公布しました。同司法解釈は2025年2月1日より正式に施行されます。
『解釈二』では、同居期間中の財産分割、夫婦間における不動産の贈与、両親による子女の住宅購入資金の負担、夫婦が第三者に贈与した財産の分割などについて、従来と比較して大幅な変更が加えられています。そこで、今回は『解釈二』の主要なポイントを簡潔に紹介いたします。
1. 夫婦間の不動産贈与:名義変更前の一方的な撤回権が消滅
夫婦間で贈与された不動産の分割について、『解釈二』では以下の2つの状況に応じた判断基準を定めています。
(1)不動産の所有権移転登記が未完了の場合
結婚前または婚姻継続中に、夫婦の一方が自身の所有する不動産を他方へ贈与、または共有名義とすることを約束した場合、登記が完了する前であっても、原則として贈与者の任意解除権は認められなくなります。裁判所は贈与の目的を考慮し、さまざまな要素を総合的に判断して分割を決定するため、裁判官の裁量が比較的大きくなります。(『解釈二』第5条第1項)
(2)不動産の所有権移転登記が完了している場合
婚姻期間が短く、かつ贈与者に重大な過失がない場合、不動産は贈与者に帰属する可能性がありますが、他方に対して適切な補償が求められる場合があります。(『解釈二』第5条第2項)
2. 親による婚姻後の住宅購入資金負担に関する財産分割ルールの明確化
『民法典』の意思自治の原則に従い、契約の約定がある場合はその約定に基づいて処理されます。契約がない、または不明確な場合は、以下の2つのケースに分けて判断されます。(『解釈二』第8条)
(1)一方の両親が全額出資した場合
不動産の名義が出資者の子女の名義で登記されているかに関わらず、裁判所は原則として出資者の子女に帰属すると判断する可能性があります。ただし、さまざまな要素を考慮し、配偶者側に対する補償の有無やその金額が決定します。
(2)一方の両親が一部出資した場合(双方の両親が出資した場合を含む)
一般的には出資割合を基準とし、共同生活の実態や子女の養育、離婚時の過失の有無などを総合的に判断して不動産の帰属を決定し、他方に対して適切な補償を行います。
なお、『解釈二』第8条には、両親が婚姻前に子女の住宅購入資金を負担した場合の財産分割ルールは含まれていません。
3. 同居期間中の財産分割ルールの明確化
婚姻関係にない同居(双方ともに配偶者がいない場合に限る)の期間中に発生した財産の分割については、約定のある場合はその内容にしたがって財産を分割します。約定がない場合または協議で合意に至らなかった場合は、「各自の所得(給与や賞与など)は各自の所有」の原則に基づいて分割されます。共同出資による不動産購入や事業経営など、財産の区分が困難な場合は、出資割合を基準に共同生活の実態や共同の子女の有無、財産への貢献度などを考慮して分割を行います。(『解釈二』第4条)
◆ 日本人駐在員および外国人の留意点
今回の司法解釈には、上記以外にも注目すべき新規定がいくつか記載されています。例えば、両親が婚姻後に子女の住宅購入資金を負担した場合の財産分割、「偽装離婚」による債務逃れの処理、夫婦の一方が共同財産を第三者に贈与した場合の扱い、夫婦の有限会社の株式分割方法などです。
中国に駐在する日本人や、中国人との国際結婚や離婚を考えている外国人は、これらの最新法規とその実務適用を正しく理解する必要があります。
中国と日本では法制度の違いに加え、文化的な価値観の違いも存在します。国際結婚においては、事前に家庭の責任や財産制度(夫婦別産制など)を話し合っておくことで、離婚時に法律や文化の違いによる争いを避けることができます。
さらに、海外の不動産やその他の財産の処理には、不動産証明書の取得や公証手続き、国内の判決が国外では執行困難となる問題などが伴う可能性があります。
したがって、中国人との国際結婚や、中国および日本国内の不動産などの資産処理が必要な場合は、中国と日本の法律に精通した弁護士に相談し、適切に手続きを行うことをお勧めします。
作成日:2025年02月14日